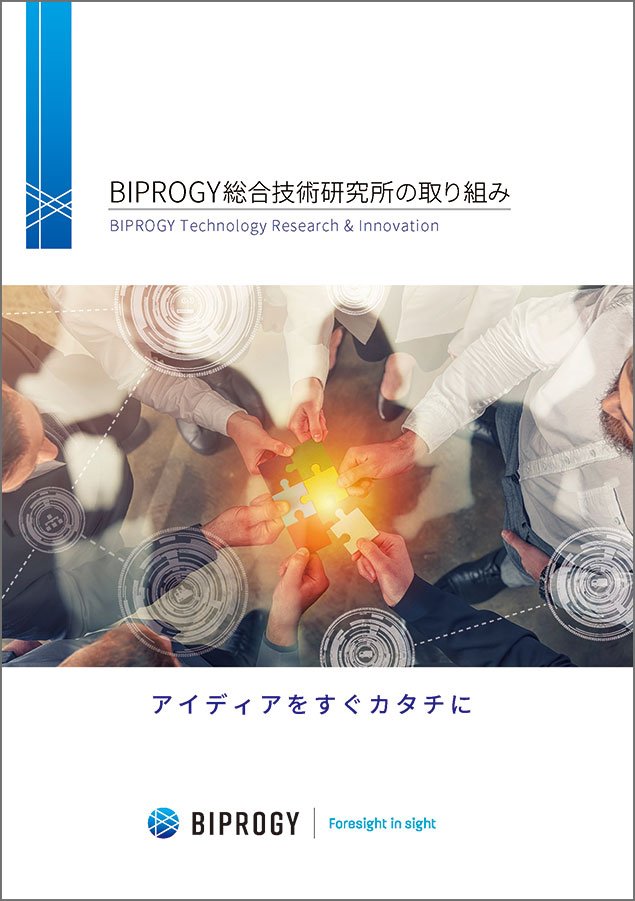BIPROGY総合技術研究所
BIPROGY総合技術研究所は、BIPROGYグループのR&Dの拠点として2006年1月に設立しました。
わたしたちは「技術を人類・社会・企業の価値に変え、持続可能なありたい未来を創造する」をビジョンに掲げています。現在の単純な延長にはない未来を技術の力で切り拓くため、形にして試しては壊して作り直してと、素早く根気よく仮説検証を繰り返す探究を「アイデアをすぐ形に」という言葉とともに大切にしています。
トピックス
-
- 2026年01月30日
- 【お知らせ】B. ボロバシュ 著 BIPROGY 総合技術研究所 川辺 治之 訳 「ボロバシュ 続 数学の技法:ケンブリッジで紅茶を飲みながら」
-
- 2026年01月27日
- 【お知らせ】国際論文誌「Journal of Digital Life」に採択論文『Why do you recall that smelly food? Effects of childhood residence region and potential reinforcing effect of marriage』が掲載
-
- 2026年01月23日
- 【講演】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム主催の『人の行動を変える「仕掛学」 ~DAY2・仕掛学ワークショップ』で講師を担当
-
- 2026年01月07日
- 【関連記事】連載「進化する総合技術研究所」 第7回 「R&D Meetup Days 2025」開催──共感と共創で社会課題解決に挑む(後編)
-
- 2025年12月24日
- 【お知らせ】『顎の形状を3次元データで可視化─大阪大学が開く医療の新たな扉』を公開
-
- 2025年12月23日
- 【講演】京都コンピュータ学院主催の高専・高校性向け生成 AI ワークショップにて『知って、遊んで、考えて、創ってみよう』と題して講演
-
- 2025年12月21日
- 【お知らせ】国際会議「IJCNLP-AACL2025」にて採択された論文『Fine-grained Confidence Estimation for Spurious Correctness Detection in Large Language Models』をポスター発表
-
- 2025年12月17日
- 【展示】大日本印刷主催のビジネスイノベーションミーティング併催イベント「技術者のワ」にて出展
-
- 2025年12月15日
- 【講演】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム主催の『人の行動を変える「仕掛学」を学ぼう! ~DAY1・仕掛学セミナー』でオンライン講演
-
- 2025年12月10日
- 【講演】BIPROGYグループ中国支店カンファレンス2025にて『「仕掛け」は世界を変える?!~誰もが楽しく社会課題を解決できる世の中の実現に向けた取り組み~』と題して講演
研究活動
人や社会と向き合い、技術の社会実装を目指す“適用実証研究・社会デザイン研究”と、数理・システム工学・生命科学分野を核に最先端技術と向き合う“先端技術研究”を両輪に、人類・社会・産業の発展に貢献する技術を送り出します。
For Human

一人ひとりのウェルビーイングを高めるために、人のメカニズムをさまざまな角度から科学的に解明することで、健康余命の延伸、物質的・心理的支援の加速、および自己の可能性の拡大に役立つIT技術を作り上げることを目指しています。
「一人ひとりの生き方が広がる社会 ―“Well-being”のためにITは何ができるか」ユニシス技報, 通巻148号 (2021)
【お知らせ】BIPROGY TERASU「『一人ひとりの生き方が広がる社会』のためにITができること」公開
For Society

より良い社会の実現を目指し、社会課題解決のための理論的な枠組みの探求と、フィールド実証を通じた業界・産業への技術適用による具体的な社会課題の解決に取り組んでいます。
【お知らせ】長野県内で進めている“持続可能性”を学ぶプログラムで活用を検討している、研究開発中の森林可視化のアプリについて取材を受け長野朝日放送「SDGs from SHINSHU」に出演
【お知らせ】「日本ユニシス 中国地方を中心とした自治体・観光協会・DMO/DMC および観光事業者とともにIoT センサーによる観光マーケティングの DX 実証実験を開始」
For Industry
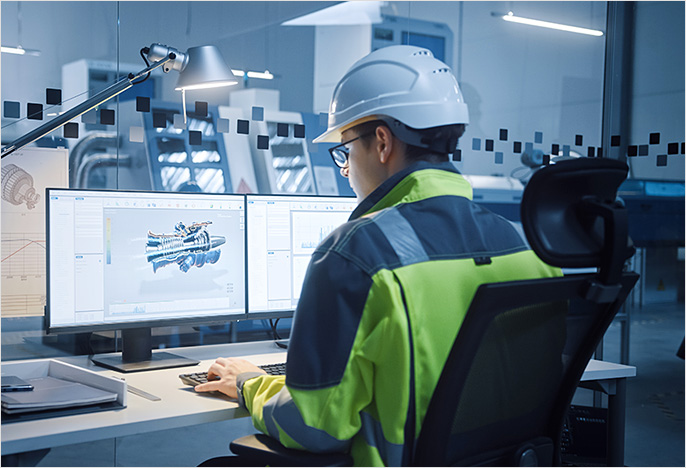
IoT/CPS環境やデジタルツイン環境がわたしたちの生活に深く浸透する中で、安心・安全性の担保と利便性の向上をデジタルの力で産業界から支えるテクノロジーの提供を目指して取り組んでいます。
【講演】第3回 AI/IoTシステム安全性シンポジウム(11/29-12/3):「Asian STAMP Workshop (Day3/Day4)」「FRAM Workshop (Day5)」に登壇
【お知らせ】Nancy G. Leveson著「CAST HANDBOOK:How to Learn More from Incidents and Accidents」の日本語版作成に協力
For Next Technology

数理、アルゴリズム、計算の力でPhysicalとVirtualを極限まで接続し、あらたな情報空間を作り出すための研究を推進しています。
【お知らせ】Chris Heunen, Jamie Vicary 著 日本ユニシス 総合技術研究所 川辺 治之 訳「圏論的量子力学」
【お知らせ】Bob Coecke, Aleks Kissinger 著 日本ユニシス 総合技術研究所 川辺 治之 訳「圏論的量子力学入門」
論文・学会講演予稿・寄稿・他
-
Yoshinori Miyamura, Ai Ishii, Atsushi Oshio
Journal of Digital Life, 6, 2 (2026) -
Fine-grained Confidence Estimation for Spurious Correctness Detection in Large Language Models
Ai Ishii, Naoya Inoue, Hisami Suzuki, Satoshi Sekine
The 14th International Joint Conference on Natural Language Processing and the 4th Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics (IJCNLP-AACL 2025) (2025), to appear -
曲線の滑らかさに関する新たな指標とその応用
土江 庄一
2025年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集 p651-652 (2025) -
A New Measure of Fairness for Curves
Shoichi Tsuchie
Computer-Aided Design (Elsevier) 190, (2026) -
二重周期境界条件を持つハミルトン流の流線トポロジカルデータ解析の数値計算アルゴリズム
坂本 啓法,長井 稔,尾島 良司,中邨 博之,坂上 貴之,横山 知郎,宇田 智紀
日本応用数理学会論文誌 35(3) p57-93 (2025) -
Interactive Intent Clarification Framework for Data Analysis Using Generative AI
Riku Takano, Rentaro Yoshioka, Takayuki Hoshino, Yukihide Kohira
The 21st International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (2025), to appear
総合技術研究所紹介パンフレット
本研究所の活動内容や取り組んでいる研究についてご紹介しています。
PDFをダウンロードしてご覧ください。
■パンフレット目次
-
ごあいさつ
-
総合技術研究所の概要
-
知識体験 ─人とコンピューターによる知識創造のためのシステム設計手法 ─
-
匂い嗜好への個人・環境特性の影響の研究
-
BIPROGYシカケラボ:仕掛学(しかけがく)の社会実装
-
共感や気づきを促す対人コミュニケーション支援
-
エコシステムのための価値循環デザイン
-
多様な人智とデジタル知能の交わるコモンズ
-
コラム:Technology Foresightのご紹介
-
天空光源シミュレーション
-
複数サービス連携時の安全性確保
-
実環境3D処理研究
-
意匠データのリバースエンジニアリング
-
流線トポロジーデータ解析
-
CPSのサイバーセキュリティ分析へのSTPA適用
-
IoT/CPSの品質検証
-
テンソルネットワークを用いた量子計算シミュレーション
-
不確実な状況における意思決定システムの研究
-
知的形状処理システムの研究
-
統計的機械学習の統合
-
数理論理学に保証された安全性
-
コラム:未来洞察~オープンイノベーションへの取り組み
-
視線情報を用いた文章読解の解明
-
医用画像診断支援システムの研究
-
IoTセンサーデータ可視化・分析による観光マーケティングDX
-
森林と未来をデザインする
-
空間認識・表現コンピューティング
-
量子ソフトウェア工学
-
名前の付いていないアルゴリズムに名前を与える
-
執筆者のご紹介
- *天空光源は、BIPROGY株式会社の登録商標です。
- *その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。