日本ユニシスの首都直下地震対策BCP・BCM
日本ユニシスの首都直下地震対策BCP・BCM
2010年10月08日掲載
日本ユニシス株式会社
事業継続プロジェクト
日本ユニシスグループは、金融業や運輸サービス業を初めとした様々な業種を含む数多くのお客様の情報システム、ネットワークに対しそのライフサイクル全般にわたったサービスを行なっています。情報システムが社会の基本的機能を維持するために不可欠になっている現在、首都直下地震のような大きな災害時にもサービスの継続を図ることは日本ユニシスグループの社会的責任であると認識し、2006年度からグループ全体でプロジェクト体制を組み事業継続に取り組んでまいりました。
事業継続プロジェクトは日本ユニシスの代表取締役を推進責任者とし、グループの各社、関連組織の代表者が月に一度程度集まり、現状問題点・課題の共有と対応推進を行なうかたちで進めています。2006年度は首都直下地震対策に取り組み、2007年春に事業継続計画書(BCP)を策定し、以後、BCM(事業継続マネジメント)として定期的な訓練をとおし対策の検証と計画の見直しを継続しています。
また、首都圏以外の地域の災害については管轄する支社を中心に、それぞれの地域事情を踏まえてBCP・BCMに取り組んでいます。
この度、日本ユニシスグループは新型インフルエンザへの取り組み状況の社外への開示(下の囲みご参照)と同様に、首都直下地震への対応方針・取り組み状況も同様にご紹介いたします。ご意見・ご質問をいただければ幸いです。
-
新型インフルエンザへの対応
2007年度から事業継続プロジェクトにおいて対策を進め、2008年8月から「日本ユニシスグループ新型インフルエンザ対策行動計画」を社外向けサイトで公開してきました。
-
こうした情報開示に積極的に取り組んだ活動はNPO 事業継続推進機構(BCAO)からアワード2009の特別賞を受賞しました。
1.日本ユニシスグループのBCPの取り組みの経緯
取り組みの経緯(首都直下地震)
| 2006年4月 | BCPプロジェクト活動開始。当初は首都直下地震対策を推進 |
| 2007年5月 | 本社災害対策本部机上訓練実施(以降、継続的に実施) |
| 2007年6月 | 「事業継続計画」承認・発効(以降、毎年見直・改訂実施) |
| 2008年4月 | 徒歩帰宅訓練開始(以降、重要業務担当者を中心に業務として定期的に実施) |
| 2008年10月 | 本社エレベータ内に閉じ込め時向け非常用ボックスを設置 |
| 2008年12月 | 全社安否訓練実施(以降、定期的に実施) |
| 2009年3月 | 本社緊急地震速報訓練実施(以降、定期的に実施) |
| 2011年6月 | 「事業継続計画」改訂実施 |
| 2012年5月 | BCPプロジェクト/本社災害対策本部の体制強化 |
2.基本方針
-
基本理念
日本ユニシスグループは、お客様の情報システムの安定稼動を支えるICT企業として、首都直下地震のような大規模災害が発生した場合においても重要業務を継続し、被災したお客様の情報システムの復旧をご支援することが社会的責任と位置づけています。
-
優先度
日本ユニシスグループの事業継続計画では以下を優先しています。
-
第一優先:従業員・役員とその家族の生命と安全を確保する。
-
第二優先:国・地方自治体の命令・指示に従い、勧告・要請を尊重する。
-
第三優先:お客様システム、ネットワークへのサービスを継続する。
-
-
帰宅方針
日本ユニシスグループは、勤務時間帯の発災の場合、国・自治体の帰宅困難者問題への取り組みへの協力と社員の安全確保のために、帰宅ルートの安全が確認されるまで事業所内に留まることを基本方針とし、備蓄その他の施策を策定しております。本社地区においては、東京都帰宅困難者対策条例に則り、一斉帰宅の抑制に協力いたします。2011年3月の東日本大震災当日においても、社員はもちろん、当社へ訪問されていた多くのお客様にも翌朝交通機関の復旧まで館内に留まっていただき、水と簡単な食糧および毛布などをご提供いたしました。
3.発災時の対応と災害対策本部
-
発災時の対応推移
首都直下地震が発生した場合は、日本ユニシスグループ本社(江東区豊洲)に日本ユニシスグループ本社災害対策本部(以下、本社災害対策本部と略します)を設置します。しかしながら、その設置と活動開始には時間がかかるものと考えられるため、発災当初は関西支社に災害対策本部(関西災害対策本部と略します)を設置し、初動の対応を行ないます。その間の状況推移を以下の表にまとめます。
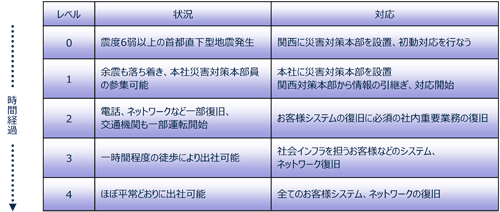
-
関西災害対策本部
震度6弱以上の首都直下地震発生の場合は、関西支社の独自判断により関西災害対策本部を設置し、主に以下の初動対応を行ないます。本社地区の被害の状況によっては、本社災害対策本部の役割(3参照)も担います。
-
従業員・役員の安否確認の状況把握
-
首都圏の主な事業所の状況確認
-
首都圏全般の被害情報(火災、道路、橋梁など)の収集
-
本社対策本部設置場所判断材料の収集と本社本部長への報告
-
本社対策本部召集
-
関連情報の事業部・他支社店責任者への伝達
-
-
本社災害対策本部
首都圏の交通機関が一部開通し、ある程度の徒歩を前提に出社が可能な状況になると、本社災害対策本部が召集されます。本社災害対策本部長は、リスク管理担当役員など3名が務めます(継承順位が予め決められています)。 本社災害対策本部の主な役割は以下のとおりですが、本部を構成する組織ごとに詳細の役割が定義されています。
-
従業員・役員の安否確認の状況把握
-
首都圏の主な事業所の状況確認
-
首都圏全般の被害情報(火災、道路、橋梁など)の収集
-
被害状況に応じた本社災害対策本部メンバーの招集
-
本社内環境維持及び救命・救護
-
被災に対する全般的な対応策の決定及び各班への指示
-
社外(マスメディアなどを含め)への当社グループ状況の報告
-
必要な資源調達申請の承認
-
支社支店(特に関西支社)と連携し、被害の早期復旧の推進
-
本社災害対策本部の解散
本社災害対策本部の体制は以下のとおりです。
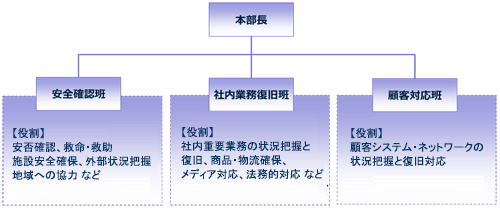
-
-
自衛消防隊
2009年に改正された「消防法」では事業所の自衛消防隊は地震等の災害が発生した場合にも一定の防災活動の役割を担うこととなりました。これを機会に日本ユニシスグループでは、事業所内の従業員や訪問者の安全確保、災害対策本部との連携など自衛消防隊の役割を明確に規定しました。
4.顧客サービスの継続
日本ユニシスグループがサービスを提供しているお客様の情報システムやネットワークが地震で被害を受けた場合、いち早く復旧してお客様の業務を継続していただくことは当社グループの社会的使命と考えています。このような考え方のもと、東日本大震災においてもいち早く復旧活動を行いました。
-
復旧の優先度の考え方
首都直下地震の場合は、被害地区に多くのお客様がいらっしゃること、また当社グループそのものも多くのリソース(従業員、事業所、設備など)が被災地に位置することとなるため、被害を受けたお客様のシステム、ネットワークの全てを一度に復旧することは困難になると考えられます。したがって、日本ユニシスグループの事業継続計画では、大地震の場合に、国としてまた社会的に早急な復旧が求められる以下のお客様のシステム、ネットワークを優先して復旧に取り組みます。
-
人命救助に必須とされるシステム、ネットワーク
-
中央防災会議による「首都直下地震対策専門調査会報告」の「首都直下地震対策専門調査会報告」の項で指定している首都中枢機能を担うシステム、ネットワーク
-
社会のインフラを担うシステム、ネットワーク
-
-
顧客サービス継続のための対応
-
コールセンターの切り替え
本社コールセンターが稼動困難になった場合は、関西地区コールセンターへ切り替え、お客様からの問合わせ対応を継続します。
-
商品配送センターの切り替え
本社地区(東京)商品配送センターが稼動困難になった場合は、関西地区の配送センターへ切り替え、商品配送を継続します。
-
社内業務システムの切り替え
平常時から本社(東京)センターと沖縄センターとの二重化運用を一部行なっていますが、本社センターのみで稼動している社内の重要業務システムが被災した場合は、沖縄センターで運用するように切り替えます。
-
サポートサービス要員派遣システム
担当要員をお客様のセンターへ派遣させるためのシステムを平常時から運用していますが、災害時には安全なルートを確認した上で派遣指示するシステムとして稼動します。
-
MCA無線、衛星電話等通信機器
本社、支社支店間の非常連絡用に配備しています。
-
5.その他の防災対策
-
災害対策本部机上訓練
-
コールセンター切り替え訓練
-
商品配送センターの切り替え訓練
-
社内重要業務システム切り替え訓練
-
クラウドサービス拠点におけるディザスタリカバリ訓練
-
安否確認訓練
-
徒歩帰宅訓練
-
eラーニング研修
-
自衛消防隊消防・防災訓練
-
緊急地震速報訓練
-
事務所における食糧・水3日分備蓄:全ての事業所に、来訪者分も含め3日分の備蓄を配備
-
エレベータ・サバイバルボックス:エレベータ内非常用ボックス(簡易トイレ、防寒シート、懐中電灯、ラジオ、水、飴、トランプなど)を配備(本社ビル)
-
本社・支社店事務所に衛星電話、MCA無線配備と定期的な利用訓練実施
-
本社・関西災害対策本部非常電話配備訓練

