日本ユニシスグループの新型インフルエンザ対策と事業継続計画(BCP)
2009年2月12日掲載
2009年4月9日更新
CSR推進部
2008年8月に「日本ユニシスグループの新型インフルエンザ対策と事業継続計画(BCP)」を公開し、多くの企業、団体からご意見をいただきました。この場を借り、御礼を申し上げます。
その後、政府の対策が進み、流行の遷移をフェーズから政府・自治体の対応の転換に重点をおいた「段階」に変更、水際作戦中心の対策から国内侵入後の対策の重視、など政府ガイドライン等が改訂されました。そのなかで、弊社を含む情報システム業界企業は、流行時にも業務の継続を期待される「社会機能維持に関わる業者」と位置付けられました。
こうした動きや最近の専門家の知見を踏まえ、日本ユニシスグループは社員や関係者の安全確保を優先しながら、社会の重要な情報システムの稼働に必要な業務をできるだけ継続するための対策として「新型インフルエンザ対策行動計画」を改訂しましたので、以下に本情報の更新をさせていただきます。今回の第二版の改訂版についてもご意見・ご質問を頂戴できれば幸甚です。尚、4月の更新では、日本ユニシス株式会社の役員担当の変更に伴い新型インフルエンザ対策本部体制図などを修正しております。
1.BCP活動の経緯
2006年度より事業継続計画(BCP)プロジェクトを設置、代表取締役副社長を責任者に、人事、総務、経営企画、事業部門、法務、システム開発サービス、保守サービス、アウトソーシングサービス、情報システム(データセンター)、情報セキュリティ推進など日本ユニシスグループの関連組織の参加により、月1回の全体会議で状況の認識、課題の確認、対策進捗の報告を行っています。また一般社員の啓発が重要であるためイントラネットを中心とした情報発信とeラーニングを活用した新型インフルエンザに関する知識と会社の規則などへの認識の向上を図っています。
2007年4月からは新型インフルエンザ対策を開始、2008年4月に諸規定を制定。5月には新型インフルエンザ対策本部の机上訓練を実施し、対策の検証とさらなる課題の洗い出しを行いました。2008年11月には従来の大規模地震向け安否確認システムに新型インフルエンザ対応の機能拡張を行い、安否報告の訓練を行いました。また、11月から12月にかけて新型インフルエンザの知識普及と会社の対応の認知向上を目的にeラーニングを実施、96%の社員が受講しました。2009年2月には、政府のガイドラインの改訂に合わせて、当社グループの「行動計画」を改訂しました。
-
2006年度から首都直下地震を重点課題に事業継続プロジェクトにより対応開始。
-
2007年8月 アジア地区出張者へのタミフル携行を推進
-
2008年3月 社員の個人生活での推奨策をつくり「新型インフルエンザ対応ガイドライン」として発表
-
2008年4月「新型インフルエンザ対応行動計画」を発効、対策本部の設置要領、全社に発令する規則を規定
-
2008年5月 新型インフルエンザ対策本部机上訓練を実施
-
2008年下期 グループ全社の全本支社店、及び協力会社への説明会を実施
-
2008年11月 新型インフルエンザ向け安否確認訓練を実施
-
2008年11−12月 新型インフルエンザ向けeラーニングを実施
-
2009年2月「新型インフルエンザ対応行動計画第二版」改訂・発効
2.新型インフルエンザ対策における基本方針
日本ユニシスグループの新型インフルエンザ対策は以下の基本方針に従い策定しています。
-
人命を最優先とする。
-
国・地方自治体の指導・勧告に従い、社会全体のパンデミック(世界的大流行)に対する取り組みに協力する。
-
安全を確保した上で、業務の継続・再開を行う。
3.新型インフルエンザ対策本部の体制と役割
新型インフルエンザが流行すると日本ユニシス株式会社社長を本部長とし、以下の構成で新型インフルエンザ対策本部を設置します。
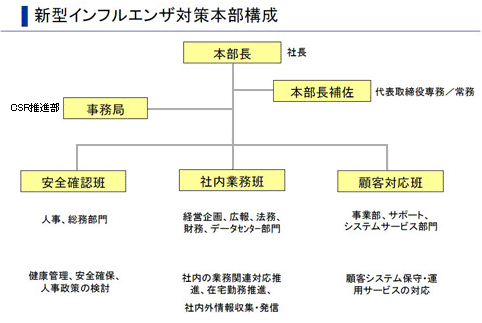
4.被害の規模に応じた対策の策定
今回の改訂の目的は先に述べましたように政府のガイドラインの改定に合わせることが大きな目的ですが、これを機会に新型インフルエンザの被害の危険度・危害規模を分類し、その被害の規模によって発令する対策を細かく分けることとしました。
新型インフルエンザはまだ発現していないウィルスによる感染症のため、現在のところ感染率、致死率がどのくらいになるか予想がつきません。1918−19年に流行したスペイン・インフルエンザのように極めて被害の大きな世界的大流行(パンデミック)となるかも知れませんし、1968年の香港インフルエンザ(風邪)のような比較的被害の少ない流行で収まるかもしれません。今回の改訂では、その点を考慮し、被害の規模(感染率、致死率)により対策を分類することにより、より適切な対策の発令をできるようにしています。これにより、過剰でなく、過小でもない、被害規模にふさわしい対策を実施することができると考えています。
被害規模の分類は、CDC(米国疾病予防管理センター)が定義する5つのカテゴリーを参考にして、日本国内の影響度を考慮して次のように設定しました。
■被害規模の想定
・重度被害:感染率25%以上かつ致死率1%以上(スペイン・インフルエンザ相当)
・中度被害:感染率10%以上かつ致死率0.5%以上で、重度被害にあてはまらない被害
・軽度被害:感染率10%未満あるいは致死率0.5%未満(1968年香港インフルエンザ、1957年アジア・インフルエンザ、通常の季節性インフルエンザ相当)
判断の基準となる感染率、致死率は、流行が確認された時点(あるいはそれ以後)で、CDCから開示される予定です。
5.段階ごとに発令する主な規定
日本ユニシスグループの「行動計画」により段階及び被害規模ごとに以下のような対策を発令します。
| (1)前段階(未発生期) | |||
|---|---|---|---|
| 各組織において、重度被害を想定し事前の対策を進めます。 | |||
|
|||
| (2)第一段階(海外発生期) | |||
| 日本ユニシスグループに、日本ユニシス株式会社社長を本部長とする「新型インフルエンザ対策本部」(以降、対策本部と呼びます)が設置されます。これ以後は、全社に対して対策本部から各種対策が発令されます。 | |||
| 発令内容 | 重度被害 | 中度被害 | 軽度被害 |
| 研修・会議・セミナー等の開催の見直し、外部セミナー等参加見直し | 実施する | 実施する | 実施する |
| 在宅勤務体制への移行開始準備 | 実施する | 実施する | 実施する |
| 出社・退社、及び勤務中のマスク着用推奨 | 実施する | 実施する | 実施する |
| 国内出張の見直し、取りやめ、海外出張の中止、海外からの受入社員の帰国勧告 | 実施する | 政府勧告に従う | 政府勧告に従う |
| 感染国から帰国した者、及び発症者と同乗した者は、3日間自宅待機。3日間発症しない場合は、職場復帰可。3日間のうちに発熱した場合は、最寄りの発熱相談センターなどへ相談(必要であれば受診)の上、結果を会社へ報告 | 実施する | 政府勧告に従う | 政府勧告に従う |
| 事業所内で発症者がでた場合は、発熱相談センターなどへ相談 | 実施する | 政府勧告に従う | 政府勧告に従う |
| (3)第二段階(国内発生早期) | |||
| 第一段階(海外発生期)での発令に加えて以下が追加されます。 | |||
| 発令内容 | 重度被害 | 中度被害 | 軽度被害 |
| 出退社途中、及び勤務中のマスク着用徹底 | 実施する | 実施する | 実施する |
| 研修・会議・セミナー等の開催中止、外部セミナー等参加中止 | 実施する | 可能な限り実施 | 政府勧告に従う |
| (4)第三段階(感染拡大期) | |||
| 第二段階(国内発生早期)での発令に加えて以下が追加されます。 | |||
| 発令内容 | 重度被害 | 中度被害 | 軽度被害 |
| 自宅勤務・自宅待機への移行強化 | 実施する | 可能な限り実施 | 実施しない |
| 不要不急の外出禁止、集会等参加禁止、研修・会議・セミナー等の開催・参加中止 | 実施する | 政府勧告に従う | 実施しない |
| 出退社途中、及び勤務中のマスク・ゴーグル着用 | 実施する | 政府勧告に従う | 実施しない |
| 出社前、本人・家族の検温とインフルエンザ症状有無確認(体温38度以上、インフルエンザ症状の咳・喉の痛み、全身倦怠感)。 | 実施する | 政府勧告に従う | 実施しない |
| 本人が発症・発症疑いの場合、一定期間出社禁止 | 実施する | 実施する | 実施する |
| 家族が発症・発症疑いの場合、一定期間出社禁止 | 実施する | 政府勧告に従う | 実施しない |
| 発症者と接触した場合は、会社へ報告して3日間(潜伏期間相当)自宅待機 | 実施する | 政府勧告に従う | 実施しない |
| 安否システムなどにより全従業員・役員の感染状況を把握 | 実施する | 政府勧告に従う | 実施しない |
| 顧客との対面はできる限り回避。社外からの訪問者は原則館内への受入禁止。対応が必須の場合は、指定の場所で対応 | 実施する | 政府勧告に従う | 実施しない |
| 事業所内で感染者がでた場合、消毒の上で使用。消毒できない場合は、2日間事務所(大部屋の場合は、周囲10メートル内)を封鎖 | 実施する | 政府勧告に従う | 実施しない |
| 顧客・取引業者への方針の説明と理解とりつけ | 実施する | 実施しない | 実施しない |
| (5)第三段階(まん延期) | |||
| 第三段階(感染拡大期)での発令に加えて以下が追加されます。 | |||
| 発令内容 | 重度被害 | 中度被害 | 軽度被害 |
| 状況(被害の大きさ、政府の勧告の深刻さなど)によっては全業務を停止し、全事業所を閉鎖 | 状況により実施する | 実施しない | 実施しない |
| (6)第三段階(回復期) | |||
| 第一段階、第二段階、第三段階(感染拡大期)での発令に加えて以下が追加されます(まん延期での発令は除きます)。 | |||
| 発令内容 | 重度被害 | 中度被害 | 軽度被害 |
| 感染状況、社会の状況などから対策本部が可能と判断する場合、安全を配慮しつつ業務再開を発令 | 状況により実施する | 該当しない | 該当しない |
| (7)第四段階(小康期) | |||
| 社会活動は流行前の状態に戻ると考えられますが、再度流行する事を前提に国内発生早期、あるいは海外発生期の状態へ戻ります。 | |||
| 発令内容 | 重度被害 | 中度被害 | 軽度被害 |
| 業務再開宣言 | 状況により実施する | 該当しない | 該当しない |
| 国内発生早期、あるいは海外発生期での対応を発令継続 | 実施する | 実施する | 実施する |
| 社員・役員の感染履歴の更新 | 実施する | 実施しない | 実施しない |
| これまでの対策の見直しと必要な是正実施 | 実施する | 実施する | 実施する |
| 備蓄の見直しと補充・拡充 | 実施する | 実施する | 実施する |
| 政府による「完全終結宣言」が出された場合は、対策本部の解散 | 実施する | 実施する | 実施する |
6.社員へのガイドライン
社員の個人生活で推奨される対策を「ガイドライン」として以下の内容を提示しています。
| (1)事前の対策 | |
|---|---|
| 情報入手 | インターネット、日本ユニシスグループのイントラネットなどの社内外情報により、新型インフルエンザに関する知識を収集し、自衛力を高めることが重要です。 |
| 通常のインフルエンザ対策の励行 | 新型インフルエンザ対策には通常の季節性インフルエンザ対策の励行が基本となります。手洗い、マスク着用、うがい、季節性インフルエンザ・ワクチン接種、人ごみへの外出を避ける、栄養のある食事の摂取と充分な睡眠など、通常の季節性インフルエンザ対策の励行を心がけてください。 |
| 食料・日用品の備蓄 | 新型インフルエンザは、1回の流行が数週間〜8週間程度続き、それが終息しても、2回、3回と繰り返し流行することが予想されています。流行の間、社会的な混乱(店舗の閉鎖や機能低下、物流機能の低下など)や交通規制により個人活動が制約される可能性があるため、日頃から最低2週間程度の食料、生活用品の備蓄を進めることを推奨します。 |
| 季節性インフルエンザ・ワクチン注射の接種 | 予防としてはワクチン注射の接種が最適ですが、新型インフルエンザ・ワクチンが製造され流通するには、発生後、半年以上もかかるとされています。一方、通常の季節性インフルエンザ・ワクチンを接種しておくと、 季節性インフルエンザには罹りにくくなりますので、インフルエンザの症状がでた場合、新型インフルエンザである確率が高いと判断できます。また、通常のインフルエンザ・ワクチンが新型インフルエンザにも一定の効果があるとの報告もあるので、新型インフルエンザ対策の一環として医療機関にて季節性インフルエンザ・ワクチン注射を接種しておくことが推奨されます。(アレルギーなどについては医師にご相談ください) |
| (2)第一段階(海外発生期)、第二段階(国内発生早期) | |
|
|
| (3)第三段階(感染拡大期、まん延期) | |
|
|
| (4)第四段階(小康期) | |
|
|
【参考情報1】政府関係省庁対策会議
| 〔前段階〕 | 未発生期 | 新型インフルエンザが発生していない状態 |
|---|---|---|
| 〔第一段階〕 | 海外発生期 | 海外で新型インフルエンザが発生した状態 |
| 〔第二段階〕 | 国内発生早期 | 国内で新型インフルエンザが発生した状態 |
| 〔第三段階〕 | 国内で、患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった事例が生じた状態。 | |
| 感染拡大期 | 各都道府県において、入院措置等による感染拡大防止効果が期待される状態 | |
| まん延期 | 各都道府県において、入院措置等による感染拡大防止効果が十分に得られなくなった状態 | |
| 回復期 | 各都道府県において、ピークを越えたと判断できる状態 | |
| 〔第四段階〕 | 小康期 | 患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態 |
(注)多くの専門家が、第一段階(海外発生期)から世界的なパンデミックへは短い期間で推移すると推定しています。
【参考情報2】スペイン・インフルエンザの被害
スペイン風邪 とも呼ばれているスペイン・インフルエンザはH1N1ウィルスによる新型インフルエンザでした。第1次世界大戦のあった1918年3月にアメリカで始まった流行は、4、5月にはヨーロッパに広がり、その後世界中に広がりました。ウィルスの毒性は、第二波では第一波に比べて比較にならないくらい高くなり、場所によっては致死率20%を超え、最悪の事態となった米国都市フィラデルフィアでは、1週間の死者が5000人を数えたとのことです。流行の期間、社会は大混乱、文字通りのパニックとなったとのことです。
通常のインフルエンザでは致死率は乳幼児と高齢者が高くなりますが、スペイン・インフルエンザでは10代、20代、30代といった年齢層で高くなっていました。これは、免疫機能が高い若年層が過剰にウィルスに反応して自らの体を傷つけたもの(サイトカイン・シンドロームと呼ばれます)といわれています。1919年(一部地域は1920年)まで続いたスペイン・インフルエンザによる死亡者は世界で4800万人から(研究者によっては)1億人と推定されています。
日本では流行の第一波は1918年、第二波は1919年、そして第三波が1920年と、3年に渡り繰り返されました。当時の総人口5500万人に対し、43%が感染し、39万人が死亡しました。平均では、死亡率0.7%、致死率1.6%になります。第二波の流行では重症度が高く、致死率は10%となった時期もあったようです。1923年の関東大震災による死亡者は10万人ですから、それの4倍近い犠牲が強いられたわけです。スペイン・インフルエンザのほかに、20世紀では1957年〜58年H2N2ウィルスによるアジア風邪、1968年〜69年H3N2ウィルスによる香港風邪が新型インフルエンザとして流行しています。前者は感染の広がりはスペイン・インフルエンザよりも大規模でしたが、症状は軽かったとされています。後者は、さらに穏やかな症状で、致死率も低かったとのことです。
参考:「新型インフルエンザ」山本太郎著(岩波新書)
【参考情報3】個人備蓄の例(出典:WHOガイド)
| 家庭において数週間分の備蓄があると望ましい品目例 | |
|---|---|
| 食料等 | 米、乾燥麺(そば、そうめん、うどん、パスタ等)、切り餅、コーンフレーク・シリアル類、カンパン、各種調味料、レトルト、フリーズドライ食品、冷凍食品(温度管理・停電に注意)、缶詰、菓子類、インスタントラーメン、ミネラルウォーター、ペットボトル・缶入り飲料 など |
| 医療品・日用品 | 常備薬(胃薬、痛み止め、持病の処方薬)、絆創膏(大・小)、ガーゼコットン、解熱鎮痛剤(アセトアミノフェンなど。薬の成分によってはインフルエンザ脳症を助長するものがあるので、医師・薬剤師に確認のこと)マスク(サージカルマスク、N95等)、ゴム手袋、水枕・氷枕、消毒用漂白剤(次亜塩素系)、消毒用アルコール、ペットフード など |
| 災害時備品 | 懐中電灯、乾電池、携帯電話充電キット、ラジオ、携帯テレビ、カセットコンロ、ガスボンベ、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、キッチン用ラップ、アルミフォイル、洗剤(衣料・食器用等)石鹸、シャンプー・リンス、保湿ティッシュ、生理用品(女性)、ビニール袋(汚染されたゴミの密封に利用) など |
【参考情報4】咳エチケット
| 厚生労働省が呼びかけているマナーで、人前で咳やくしゃみをする場合には以下を注意する |
|---|
|
【参考情報5】参考サイト・文献
-
山本太郎著「新型インフルエンザ−世界がふるえる日」(岩波新書、ISBN-13: 978-4004310358)(新書)
-
岡田晴恵著「H5N1−強毒性新型インフルエンザウィルス日本上陸のシナリオ」(ダイヤモンド社、ISBN-13: 978-4478002407)
-
J.M.Barry著「グレート・インフルエンザ」(共同通信社、ISBN-13: 978-4764105508)

