事例紹介
世田谷区と日本ユニシスが共同開発した先進のサービス「街づくり情報システム」
世田谷区役所様
ソリューション、製品・サービス
- INTERVIEW
- 「街づくり情報システム」とは?
- 東京23区で最大の申請件数をカバーするためのシステム
- ES7000の選択において、求められた条件
- ITシステムの導入が、役所の縦割り行政の仕組みを打破
- 街づくり情報システムはまだまだ発展途上。これからのプランは?
- 今後、日本ユニシスに求めること
2004年11月04日
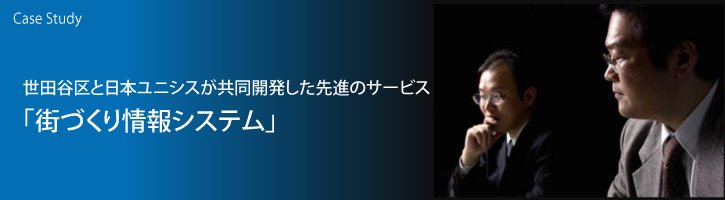
世田谷区では、「街づくり情報システム」という新しいしくみで住民サービスの向上を実現している。このサービスは、世田谷区が日本ユニシスとともに開発したもので、その中心で動いているのは、「Unisys Enterprise Server ES7000」(以下、ES7000)だ。
そしてこのシステムには、他地域の行政機関などからの視察が絶えないほどに、大きな注目が集まっている。そのもっとも大きな理由は、システムが生み出す質の高いサービスとともに、システムを入れたことで、役所の縦割り構造が打破されたところにある。
今回は、現在、「街づくり情報システム」をはじめとするITシステムを管理する都市整備部の遠藤幸宏係長と石川裕一主事に、導入の経緯や苦労したところ、また、その将来像などを語っていただいた。
本事例に掲載された情報は、取材時点のものであり、変更されている可能性があります。なお、事例の掲載内容はお客様にご了解いただいておりますが、システムの機密事項に言及するような内容については、当社では、ご質問をお受けできませんのでご了解ください。
INTERVIEW

都市整備部
都市環境課
計画調整担当係長
遠藤 幸宏 氏

都市整備部
都市環境課
主事
石川 裕一 氏
「街づくり情報システム」とは?
家やビルを建てるなど、「街づくり」を実現するためには、建築、土木、都市計画など、幅広い分野において法律問題をチェックしたり、申請を行ったりしなくてはならない。それを統括的に扱えるように工夫されたシステムが、世田谷区とユニシスが共同開発した「街づくり情報システム」(略称:IDES)だ。まずは、街づくり情報システムというのがどういったものなのか、そのあたりから聞いていってみよう。

— 世田谷区が運営している「街づくり情報システム」というのは、どういった仕組みなのですか?
遠藤氏:たとえば、家を建てようといったときには、さまざまな確認や申請が必要になります。自分の持っている土地には家が建つのだろうか、といった基本的なところについては、建築基準法をチェックしなくてはなりません。前にある道路には規制はないのだろうかと、道路管理に関する法律も調べなくてはなりません。そもそも、その道路は公道なのか、私道なのかといった素朴な疑問に対する確認も出てきます。ほかにも、このエリアの都市計画はどうなっているのだろうか、などなど、とにかく、非常に幅広く法律などの諸要件と照らし合わせていかなくてはならないのです。
— なるほど
遠藤氏:一般的な役所では、そうした1つひとつの問題について、別々の所管が相談や申請を受け付けるわけです。しかしそれだと、区民の方にすると、1つの家を建てたいだけなのに、あちこちの所管をぐるぐると回らなくてはなりません。そしてそれは、役所内の職員も同様で、1つの案件について、あちこちの所管を回らなくてはならないのです。
— その感じ、わかります。
遠藤氏:そこで、私たちが考えたのは、1つの案件があったとしたら、その案件についてのデータを入力し、それを、必要なすべての所管で参照できるような共通のデータにできたら、区民の方にせよ、私たち職員にせよ、あちこち回る手間は減るだろうということでした。
— それを実現したのが、街づくり情報システムというわけですね。
遠藤氏:そうです。街づくり情報システムの基本は、一言でいえば、「地理情報システム(GIS:Geographical Information Systems)」です。世田谷区の街づくり情報システムの場合ですと、まず、すべての所管が共通で使える地図データがあります。そして、その上に、各所管が、担当する専門情報をレイヤーの形で乗せていて、他の所管からでもその情報が参照できるようになっているのです。
— 各所管が協力しあって、地図を元にしたデータベースを構築し、そしてその情報は共有されている仕組みというわけですね。
遠藤氏:はい。実際の業務の流れから見てみると、はじめは、区民の方の事前相談ですね。必要とされる情報は、そこで一括して参照できます。また、そこで、区民の方のデータが入力されると、そのデータは各所管へと流れていきます。所管から所管にバトンタッチされる形で、必要な作業がスムーズに進んでいくのです。
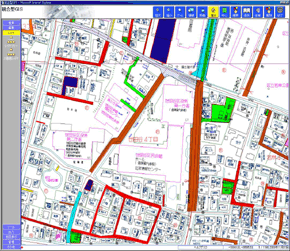
東京23区で最大の申請件数をカバーするためのシステム
街づくり情報システムは、役所の職員にとっても、相談に訪れる区民にとっても使い勝手のよい形になっている。さて、その導入の経緯はどういったものだったのだろう。

— 街づくり情報システムの導入の経緯、また、その基本的な企画趣旨を教えてください。
遠藤氏:そもそもは、建築行政における確認申請等の手続きを円滑にできるようにといった考えからスタートしています。いまはもうないのですが、「建築調整課」という所管の主導で、各種申請の受付業務からスタートしました。
— 従来の紙業務を、コンピュータを使ったデジタル業務に切り替えるシステム作りに手を付けていった、というわけですね。
遠藤氏:実を言いますと、いまのシステムの前の段階でも、すでにシステムはあったんですよ。システムはあったのですけれど、使い勝手もあまりよくなくて、また、思うように動かなかったのです。そこで、役所の職員が使いやすく、なおかつ、お客様へのサービスがアップするようなものを作っていこうと考えるようになりました。
— すると、システムの新規構築ではなく、入れ替えという感じだったのでしょうか?
遠藤氏: ええ。以前のシステムも日本ユニシスが入れていたのですが(笑)、その日本ユニシスに、「何とかならないか」と声を掛けたのが始まりだったと思います。
— 現在のシステムを導入する以前の状況というのは、どのようなものだったのでしょう。
遠藤氏:当時の世田谷区は、東京23区内で最大の面積と人口を持つ区でして、当然、建築関係の申請数も、23区内で最大級でした。世田谷区では区域を5つに分け、それぞれに支所を設置し、窓口業務をしているのですが、以前は、5つの支所はそれぞれに、個別に稼働しておりまして、また、都市計画、建築確認、道路管理関係などは、本庁だけで扱っていたため、とても不便だったのです。
— といいますと?
遠藤氏:たとえば、支所を訪れる人にしてみれば、「玉川管内も見たいが、烏山管内も見たい」という話になります。そのときに、データが紙だと「そのデータはここにはありませんので、担当の支所へ行ってください」ということになってしまうわけです。しかし、それでは不便ですので、私たちは、どの窓口でも、案内から確認書類までを受け付けられるようにしようと考えたわけです。
— なるほど。区民の方にしてみれば、その方が断然便利ですね。
遠藤氏:ええ。システムの構築に際して、その根本で私たちが大切にしていたのは、「区民に対するサービスの向上」ということでした。情報提供サービスが迅速、高速に行えるシステムを実現したいというのが、システム開発のおおもとのコンセプトですね。
ES7000の選択において、求められた条件

世田谷区のITシステムは、大きな展望のもとに導入されている。以前からの関わりで、日本ユニシスにシステム構築を依頼したということだが、ES7000以外の選択肢はなかったのだろうか。
— 以前からの関わりで、日本ユニシスにシステム構築を依頼したとのことですが、ES7000以外の選択肢はなかったのですか?
遠藤氏:導入するハードウェアに関してもっとも重要視したのは、「演算処理の速さ」ということでした。そのほか、増加するデータ量に対応することも大切ですし…。あとは、「止まらない」ということも絶対条件ですね。ES7000は、それに当てはまっていました。
— 街づくり情報システムを含む区役所全体のITシステムは、どのような構造になっているのですか? たとえば、回線スピードなどは?
遠藤氏:平成11年の段階では、1.5Mbpsの線でやっていました。それが、平成12年に、国から高度情報通信基盤整備のための補助金を受けられることになりまして、100Mbpsの光通信網で結ぶことができるようになりました。街づくり情報システムも、この基盤に乗って改修をしていき、Web化という形態へと進化しました。
— 接続形態は、どういった形でしょう。

遠藤氏:庁内には第1から第4までのネットがありまして、街づくり情報システムは第2ネット内にありまして、そこでES7000が動いています。それがループ状につながって、仮にどこかのラインが途切れたとしても、別のラインからつながっているという仕組みです。
— 現在、ES7000上では、どのようなシステムが動いているのですか?
遠藤氏: ES7000上では、街づくり情報システム、住居表示システム、防災システムが動いています。マシン自体は1台なのですが、その内部をクラスタ分割して稼働させています。
— いままでに、トラブルが起きたことは?
遠藤氏: ありましたよ(笑)。システムの改修段階に、テスト環境では大丈夫だったものが、本番で落ちてしまったというものでしたね。もちろん、落ちたといっても、システムが止まってしまったわけではありません。2つのクラスタに分かれていますので、片方が止まったときには、もう片方がフォローをしたという状況です。
— 街づくり情報システムの中核を担う地図情報は、どういったソフトが使われていますか?
遠藤氏: 「MapQuest」という地図エンジンが動いています。
— それを選んだ理由はどういったところでしょう?
石川氏: MapQuestがWeb対応になっていたというのが、採用の最大理由ですね。そのほか、性能はもちろんですが、安価であったこと、ライセンスフリーであったことなどの理由から選択しました。
— 情報提供は、日本ユニシスからですか?
遠藤氏: そうです。日本ユニシスのSEが提案してくれました。システム改修の際に世田谷区から出した条件は、「ネットワーク基盤ができたので、WebGISに切り替えたい」、「端末ごとのライセンスはコスト面で厳しい」、「エンドユーザーにとって手軽に使える仕組みが欲しい」といったものでして、それに対して、日本ユニシスは、3つぐらいの候補を用意してきてくれました。
— 実際に導入してみて、どうですか?
遠藤氏: 以前のシステムと比べると、ユーザー端末に、何も入れなくてもいいようになっている点がよいですね。新たにライセンスが必要になるのは、Adobe Acrobatぐらいのものだと思います。
ITシステムの導入が、役所の縦割り行政の仕組みを打破
世田谷区の運営する街づくり情報システムには、全国の自治体などから視察が訪れるという。そこまで注目されるのは、いったいなぜだろう。導入、運営の際の苦労などとあわせて、その核心に迫ってみよう。

— 導入以来、ここまで育ててくるには、大変だったのではないですか?
遠藤氏:事例があるわけではないので、大変といえば大変でしたね。まず、導入時には、今でこそ電子自治体といった流れがあるものの、その当時はまだ、Windows® も95から98になろうかという時期でしたので、パソコン自体に触ったことのない職員もいた状況です。それがいきなり、電子情報に切り替えて、共有できるようにしようと…(笑)。
— しかし、全国に先駆けてスタートさせたことで、いまでは、さまざまな自治体などから視察に訪れるとのことですが…。
石川氏:視察は多いですよ。年間に十数件はありますね。
— どういったところが多いですか?
石川氏: 東京23区をはじめ、都道府県レベルでもお見えになりますね。総務省、国土交通省などの情報関連の担当官の方もお見えになります。
— 視察に来られた方からよく質問されるのは、どういったことですか?
遠藤氏: まず、導入されている装置関連、あと、開発コストとランニングコストが気になるという方が多いようです。ほかに事例があるわけではありませんので、参考にしていかれるようですね。
— なるほど。
遠藤氏: あと、お見えになった皆さんが「よくこれだけ、縦割りを打破する仕組みができましたね」と驚かれます。こちらとしても、このITシステムの一番の効果というのは、そこだろうと思っています。

— そのあたりについて、もう少し詳しく、教えていただけますか?
遠藤氏: あまりよい言葉ではありませんが、「たらい回し」という言葉をお聞きになったこと、ありますよね。実は、役所内のそれぞれの課というのは、法律ごとに分かれた組織になっているのです。他の課というのは所管する法律が別ですから、相互の情報交換はあまりありませんでした。そのために、たらい回しといった現象が起こってしまうのです。
— お役所の大きなデメリットとされている問題ですね。
遠藤氏: そうですね。しかし、当区の場合には、このシステムができたことで、公開できるデータについては、どの所管からもアクセスができるようになりました。
— しかし、データの入力は、大変な作業だったのでは?
遠藤氏: 入力自体は大変だったと思いますが、何しろ、入力しないと、情報が出てきませんから…(笑)。ある所管が入力した情報のおかげで、ほかの所管では、統計が取りやすくなったなどのメリットが出てきます。大変な作業をした結果、データの二次利用が可能になって、役所のトータルとしては、スムーズになったと思います。
— いままでは縦の流れしかなかった業務体系が、部署が横につながる業務体系に変化することができたということですね。
遠藤氏: はい、そういうことです。ほかにも、このシステムの活用により、行政訴訟が起こりにくいという点もあると思います。
— といいますと?
遠藤氏: 役所の業務にとって、正確さというのは非常に重要な問題です。情報の案内を間違ってしまうと、本来は建ててはいけないところに、建物を建てようといった計画が持ち上がってしまうこともあります。それが、行政訴訟にまでいってしまったりするのです。直接画面を見ていただいて、ご確認していただくという仕組みが、ひいては、行政訴訟などのトラブルを回避することになるわけです。
街づくり情報システムはまだまだ発展途上。これからのプランは?
職員自らの利便性からスタートしている世田谷区の街づくり情報システムは、いまや、職員たちだけのものから、防災、福祉など、市民のためのものへと移ってきている。まだ、発展途上段階にあるシステムの今後については、どういったことが考えられているのだろう。
— 街づくり情報システムの今後については、どういった方向が検討されているのでしょう。
遠藤氏: これからやっていかなくてはならないことは、データの運用ですね。今のところ、個人情報などの絡みもあって、外にはつながっていないのですが、昨今のインターネットの普及などを考え、今後は外に開くことが必要と考えています。
石川氏: 民間やNPOなどは、地図に載せられるアイディアもいろいろとお持ちになっているのではないかと思います。たとえば、ルート検索ナビゲーション的なものなど、役人の視点ではなかなか気づかないようなものもあるはずです。このあたりは、どちらかといえば、環境整備になるのかも知れませんが、そうしたものが実現できればと思っています。
— それは楽しそうですね。それで、具体的には、いつ頃からサービスが出てきますか?
遠藤氏: 具体的な時期は明確ではありませんけど…、すでにいろいろなアイディアは検討していまして…。とりあえず、一般に開いていくのは、来年度の課題ですね。遊びでもいいから、地図を利用した“何か"ができるといいかと思いますね。
石川氏: どんなデータでも、載せようと思ったら載せられるということが大切ではないかと思います。アイディア募集も、16年度の取り組みでやっていきたいと思います。
遠藤氏: いまはあくまでも、役所の中だけの統合利用ですが、これからは、区民の方にも、民間も含めて、地図のデータを共有してもらうということが大切でしょうね。民間の団体も含めて、一つの共有空間データベース上で、いろいろな情報のやり取り、データ共有ができれば、経済活動も活発になるのではないかと…。これは、われわれの仕事ではないかも知れませんが…(笑)。
— 16年度に、期待ですね。
遠藤氏: はい。期待していてください。
今後、日本ユニシスに求めること
最後に、日本ユニシスについての感想や今後の要望について、お伺いしておこう。

— さて、最後になりますが、現在のシステムについては、ご満足ですか?
遠藤氏: 担当者としては、満足ですね。まず、最初の開発の段階で、あれだけの仕組みを作って、それが動いてくれたというところに、正直、驚きました。すごいな…と。ちなみに、Web化については、速度面などでさらなるブラッシュアップをしていくために、もう少しチューニングに時間がかかるのではないかと思っています。
— 日本ユニシスに対しては、いかがですか?
遠藤氏: Web化にあたって、「Microsoft® .NETテクノロジー」を提案し、選択させてくれたことは、高く評価しています。当時はまだ、名前だけしかわからないものをあえて選択して、システムが作れたことは、すごいと思いますね。おそらく、世田谷区のシステムのほかには.NETを利用した大規模な仕組みは、まだ出てきていないのではないかと思います。新しいものにチャレンジして、ちゃんと動かしてくれたというのは、素晴らしいと思いますね。
— 今後、日本ユニシスに対して望むところがあれば、お伺いできますか?
遠藤氏: ITの世界というのは、仕組自体の変化が速いので、ついていくのが大変です。新しい技術について、技術屋としての視線から、いろいろとアナウンスをしていって欲しいですね。情報提供とチャレンジ、そして、アドバイスを望みます。
これまで、役所といえば、“おかたい"イメージが既成概念としてできあがっていたものだ。組織の構成上、仕方がないとはいえ、それは現実のことだったと言ってよいだろう。そういう現状にあって、世田谷区役所では、ES7000を核としたシステムを導入することで、縦割り構造をとてもスマートに打ち破ってみせた。その上、まだまだ今後、幅広く区民を巻き込んださまざまな発展を見せていきそうだ。世田谷区役所の今後の動向に注目し、期待していきたい。

- *Adobe、Acrobat Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステム社)の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- *MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- *Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- *その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

